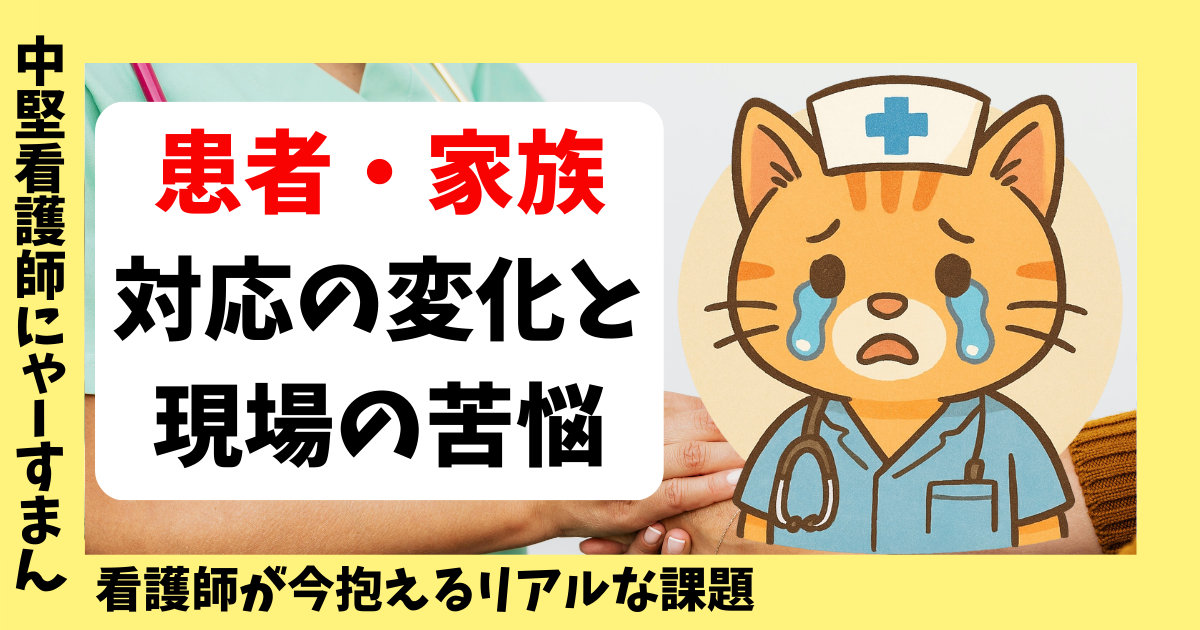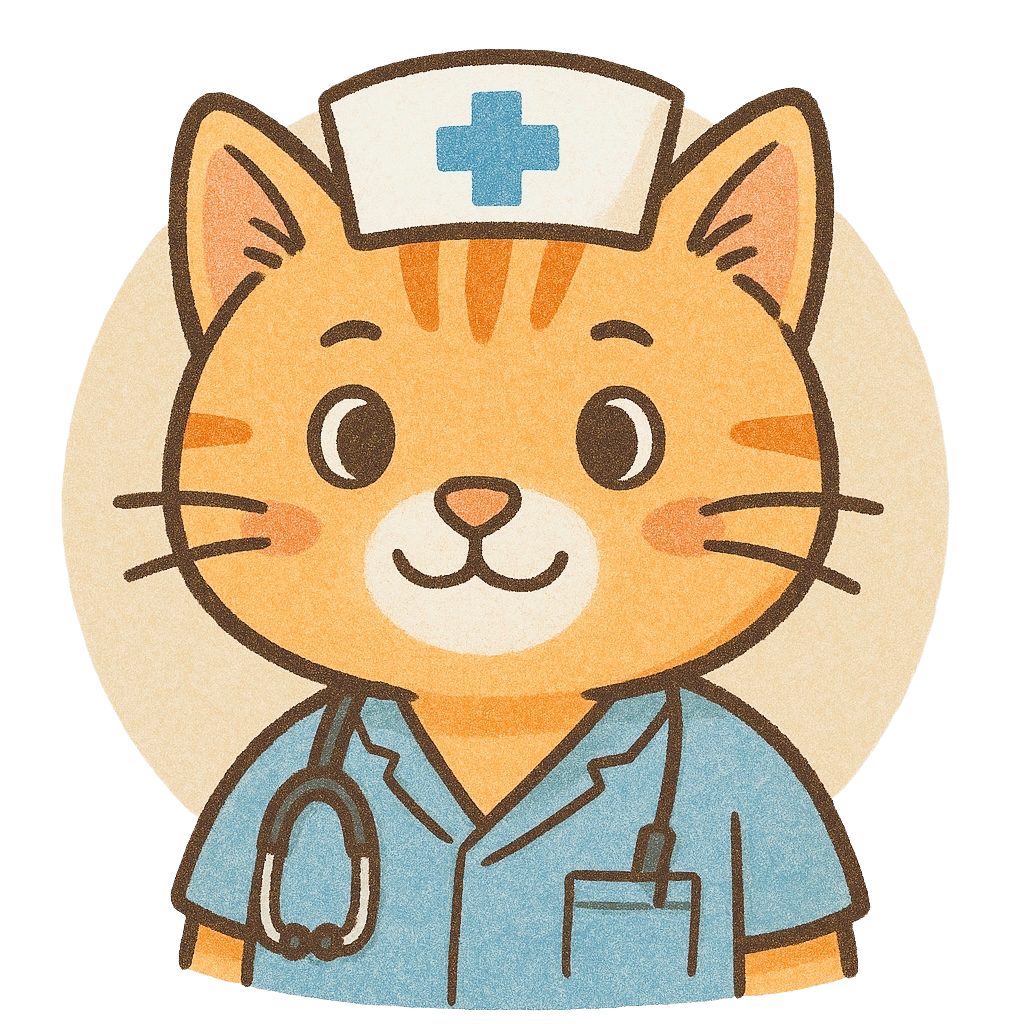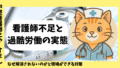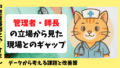みなさん、いつもお疲れさまです!中堅看護師にゃーすまんです!
「前より患者さんやご家族の要求が厳しくなっていない?」看護の現場において患者やその家族の対応に困った経験がない人の方が少ないと思います。優しい感謝の言葉をいただく一方で、心ないクレームや過度な要求に消耗するケースも増えてきました。「この要求、どう答えれば…?」と戸惑う対応が増えているのではないでしょうか。
今回の記事はそんな現場の悩みや苦悩を、読者の共感と信頼を得る形で共有すると同時に、具体的にどう対処していけばいいかを見ていきます。
1. 「モンスターペイシェント」対応の増加傾向
厚生労働省や学会の調査によると、医療従事者が直面するトラブルは年々増加傾向にあります。
👉 つまり、今や「年に1回あるかどうか」ではなく、「日常的に直面するリスク」になっています。

にゃーすまんも患者からの暴力はもちろん、暴言を吐かれたことは何度もあるよ。認知症の患者さんが増えてきていることもあるけど、それに耐えられない看護師がいてもおかしくない状況だと思うよ。
2. 「ペイハラ」として注目される新しい問題
近年は「カスタマーハラスメント(カスハラ)」に加え、「ペイシェントハラスメント(ペイハラ)」という言葉が使われるようになりました。
厚労省も「カスタマーハラスメント(ペイハラ)」として規制を強化していますが、医療現場への浸透には時間がかかっているのが現実kango.medica.co.jp。

実感としてペイハラを受けたとしても管理者側が動いてくれることは少ないかな。結果として被害受けた看護師側が泣き寝入りするのが多いように感じるよ。
3. なぜ患者・家族の対応が変わったのか?
背景には複数の社会的要因があります。
情報化社会
インターネットで医療情報を容易に得られるようになり、「知識武装」した患者や家族が増加。正しい情報もあれば、誤情報もあり、現場と認識のギャップが生じやすくなっています。看護師はただ医療を提供する存在ではなく、見られ、判断される相手になっています。
高齢化と多疾患併存
認知症患者や複数の持病を抱える方が増加。そのケアを担う家族の負担が大きく、結果的に要求や不満が医療者に向けられるケースも。
サービス業化する医療
日本ならではの「患者はお客様」という考え方が根強く、過剰な「顧客対応」が医療現場にも浸透。しかし、医療は本来「人命を守るサービス」であり、過度な要求すべてに応えるのは不可能です。

看護師だって全ての医療に対する知識が「完璧」なわけじゃないよね。ネットの情報に追いつけないこともある。患者やその家族の「理想の看護師像」で関わられても困ることがあるよね。
4. 現場の苦悩と実際の声
現役看護師からはこんな声が聞かれることが多いのではないでしょうか。
👉 これらは珍しいケースではなく、日常業務に組み込まれてしまっている現実があります。精神的負担が蓄積し、うつ病やバーンアウトの原因にもなっているのが現場の実情です。

今ではある程度のところで話を切り上げられるスキルが身についたけど、新人や真面目な看護師は苦労する場面だよね。「患者さんの要望に応えられなかった」と思い悩んで鬱になった同期もいたよ。
5. 看護師が取れる具体的な対応策
もちろん「仕方ない」で終わらせることはできません。現場でできる工夫を整理します。
- チームで共有する
苦情やハラスメントは「自分だけの問題」として抱え込まない。カンファレンスや申し送りで情報をオープンに。 - 記録を残す
発言内容・日時・状況を記録し、必要に応じて管理職に報告。エビデンスがあることで対応がスムーズに。 - 共感の言葉を添える
「ご不安なお気持ち、よくわかります」など、まず気持ちを受け止める言葉を挟むとクレームが和らぐ場合が多い。 - 限界を超える要求には線引きを
「医療安全のために対応できないことがあります」とはっきり伝える勇気も必要。

何か違和感を感じたらまず他の看護師に「こう感じた」と伝えてみるのが第一歩だと思う。その看護師も「おかしい」と感じたなら恐らくそれは間違いのない「違和感」だね。そこからチームへの相談、対策を練っていくのがより安全で効果的だと思うよ!
まとめ
患者・家族対応の変化は、医療の社会的背景とリンクしています。看護師として「心を守る対応力」を磨くことは、自分を守る第一歩になります。
次回は、管理者とのギャップに焦点を当て、「師長も変えられない構造の中で苦しんでいる背景と関わり方」について考えていきましょう。