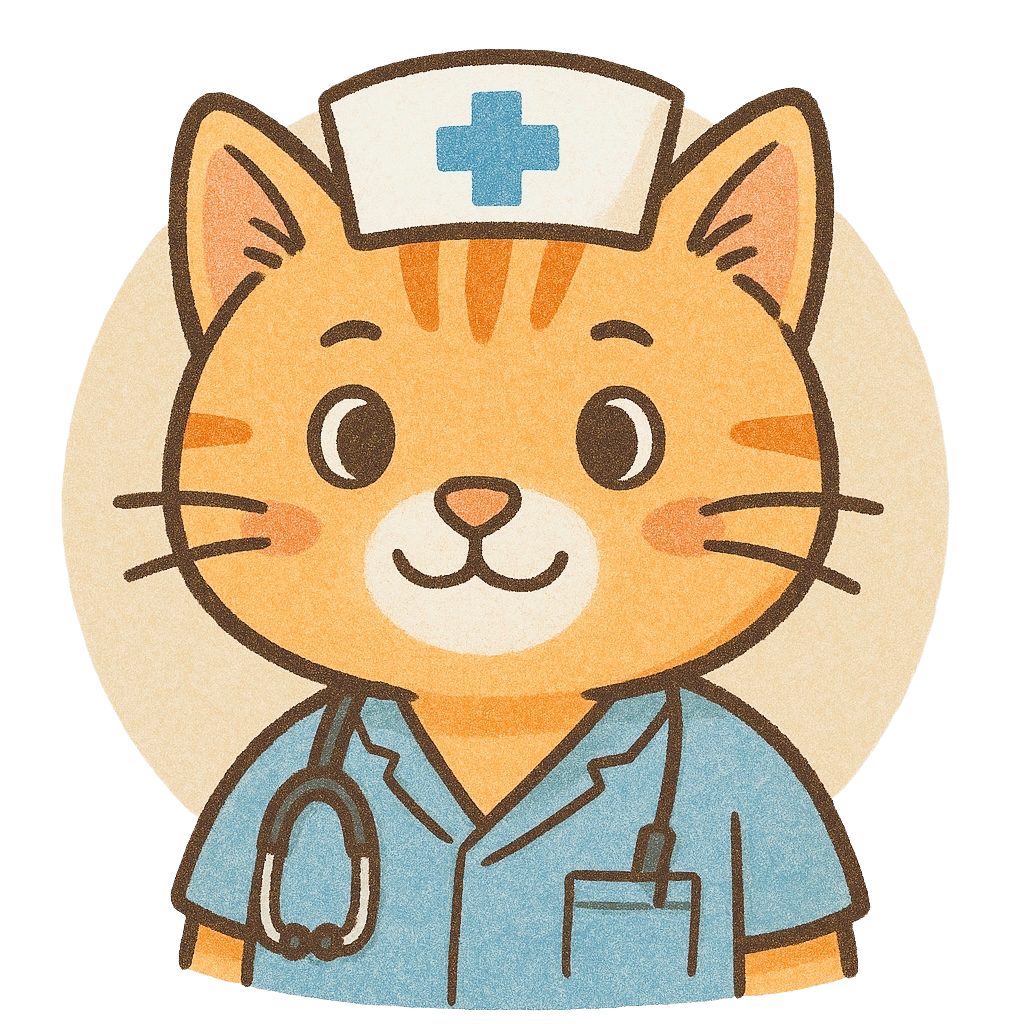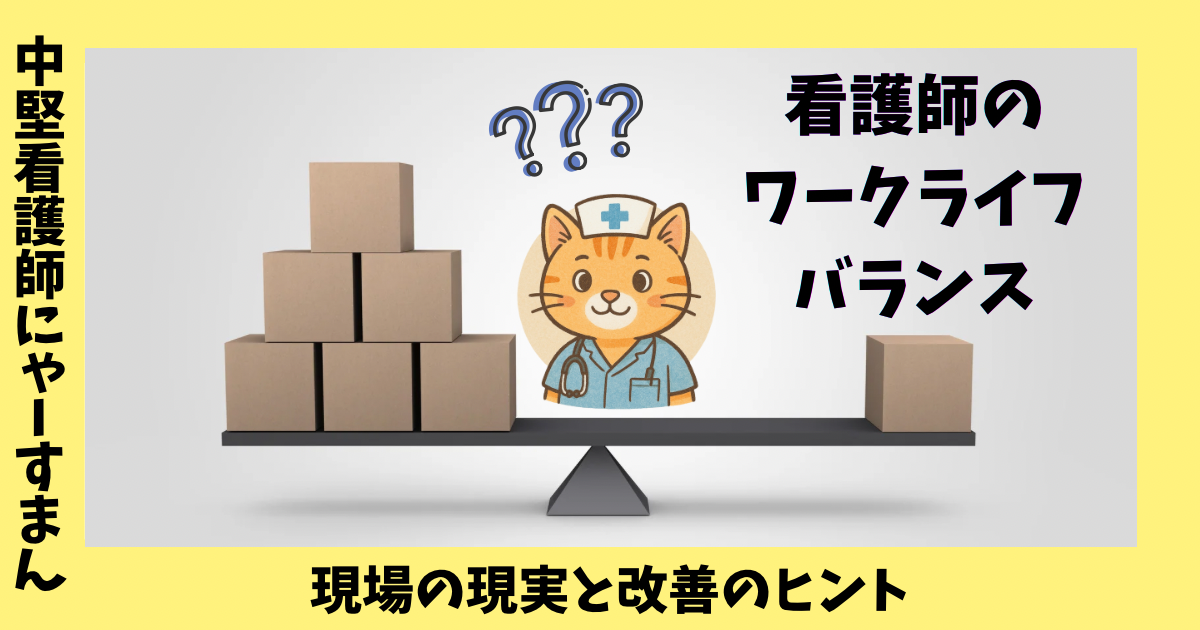みなさん、いつもお疲れさまです!中堅看護師にゃーすまんです!
看護師は「命を預かる」責任の重い仕事を担っています。
やりがいや誇りがある一方で、心身の疲弊からメンタル不調に陥る人も少なくありません。
厚生労働省の調査によると、看護職の約3割が「強いストレスを抱えている」と回答しており、一般職種に比べて高い傾向があります。
この記事では、看護師のメンタル不調の実態と、そのサイン、そして予防や対処の方法について解説します。
看護師のメンタル不調の実態
- 人間関係のストレス(同僚・医師との関係、患者・家族対応)
- 過重労働(残業・夜勤・休日出勤)
- キャリア停滞への不安(学びの時間が取れない、昇進・転職の迷い)
- プライベートとの両立の難しさ(家庭・育児と仕事の板挟み)

メンタル不調の理由は本当にたくさんあるよね。自分が何に一番ストレスが感じやすいのかということを一度整理しておくことは大事だね。後々、自己分析に役立つから普段から意識しておくことをおすすめするよ。
データで見る看護師のストレス
- 日本看護協会の調査(2022年)では、「精神的にきつい」と回答した看護師は約60%。
- 特に 20〜30代前半の若手看護師の離職理由として「メンタル的に持たない」が上位に挙げられています。

20〜30代前半は「自分とは何者か」ということを考える時期でもあるから、精神的に不安定な人が多いように思うよ。自分の目指す働き方ではなかった時にメンタルが崩れて行きやすいのかもしれないね。
バーンアウト症候群とは?
“バーンアウト(燃え尽き症候群)”は、強い使命感や責任感を持つ人ほど陥りやすい状態です。
看護師に多い症状としては:
- 情緒的消耗感(感情が枯渇したように感じる)
- 脱人格化(患者や同僚に冷淡になる、自分を守るために距離を置く)
- 個人的達成感の低下(「何をしても意味がない」と思う)
これらが重なると、仕事への意欲が急激に低下し、最悪の場合は退職や長期休職に至ります。

にゃーすまんも異動する前は、上の3つ全て当てはまっていたよ。業務が忙しすぎて自分の理想とすることができない、それによって誰の役にも立てていないと思っていた時があったね。当てはまる人はもしかしたら“バーンアウト”かもしれないね。
職場でできる予防策
- 相談体制の整備:産業医やメンタル相談窓口を気軽に利用できる環境
- 業務量の調整:夜勤回数の見直し、チームでの負担分散
- 管理者の理解:師長・主任が「心のサイン」に敏感になること

もし自分が“バーンアウト”かもしれないと少しでも思ったら、信頼できる人に早めに相談した方がいいよ!師長でも先輩でもメンタル相談員でも。にゃーすまんは信頼できる看護師の友人に“ありのまま”思っていることを話したら「自分の軸」が見えてきたよ。相談することで自分にとって何が大切なのか見えてくると思うよ。
個人でできる予防策
- セルフケア
・十分な睡眠と栄養
・趣味やリラックス法を持つ - 思考の切り替え
・「できなかったこと」ではなく「できたこと」に目を向ける - 専門家のサポートを受ける勇気
・心療内科やカウンセリングを早めに活用する
・「弱さ」ではなく「自分を守る手段」として位置づける

趣味を持つことは本当に大事なことだと思う。それが「逃げ場」になるからね。「これがあるから頑張れる」という気持ちはとても心の支えになってくれると思うよ。もしそれが難しいようなら専門家のサポートを受けることも大事になってくると思うよ。まずは自分の気持ちを整理して「本当の自分の気持ちを知る」ことが第一歩だと思うよ。
助けを求めることの重要性
日本では「看護師は強くあるべき」という風潮があります。
しかし、自分の心を守ることは、患者を守ることと同じくらい大切です。
一人で抱え込まず、信頼できる同僚・上司・専門機関に早めに相談することが、バーンアウトを防ぐ大きな一歩になります。

自分の心を守れなかったら、患者の心も守れないと思っているよ。まずは自分のことを優先していいと思う。自分のことをもっと大切にして行きましょう!
まとめ
看護師のメンタル不調は「特別なこと」ではなく、誰にでも起こりうるものです。
- 実態を知る
- バーンアウトのサインを理解する
- 職場と個人、両面で予防に取り組む
これらが揃って初めて、安心して長く働ける環境が整います。